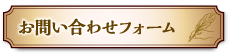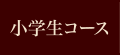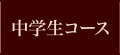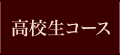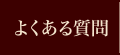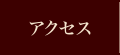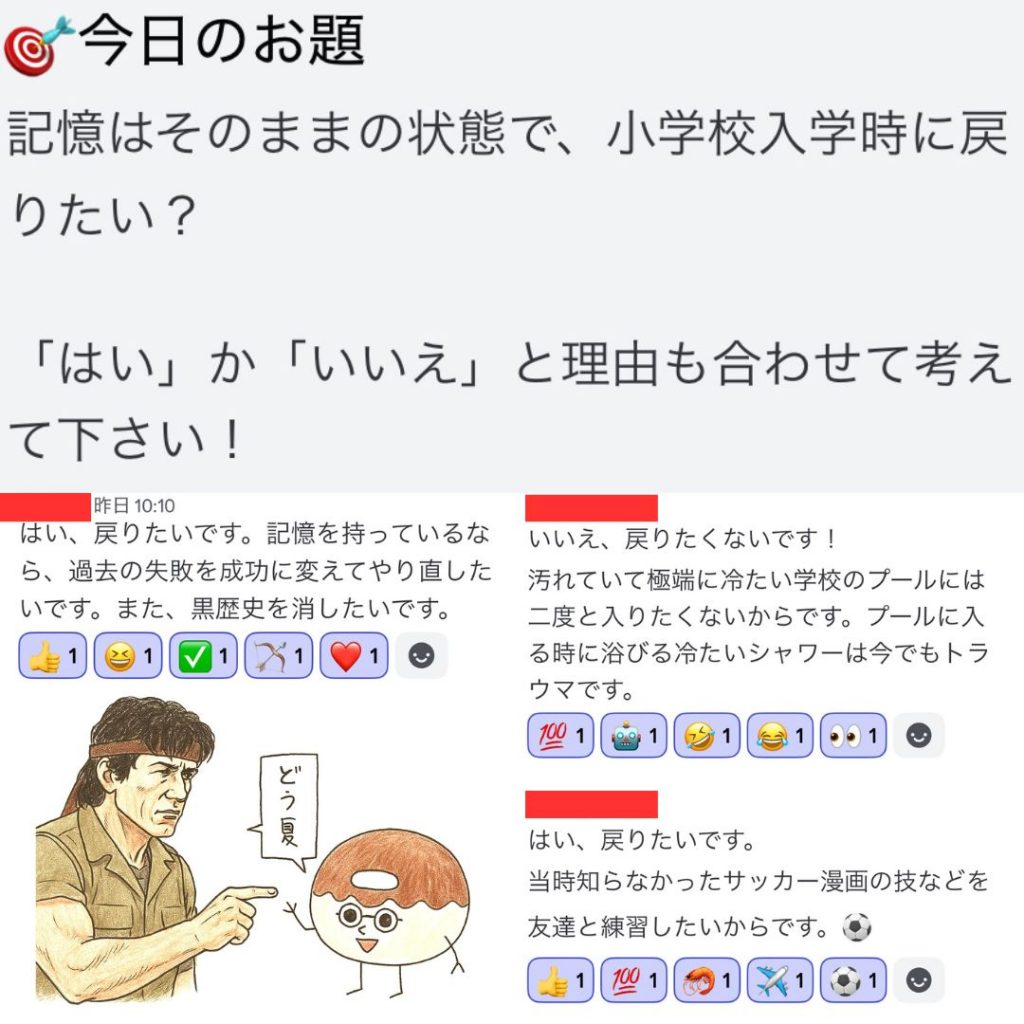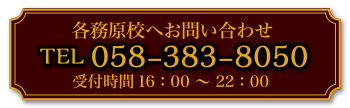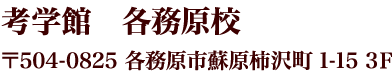当塾の全てのSNS(大学合格実績も2025版に更新済)
→https://lit.link/takashimizunogtmsteam
▲隅々までご覧下さい。
学力低下の背景と、私たちができること
文部科学省が実施する全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果が公表されました。小6・中3を対象とした主要教科の平均スコアは、数学を除く4教科で前回調査より低下。子ども全体の学力低下がこれほど顕著に表れたのは、実に20年ぶりだといいます。
一方で保護者への調査では、平日に1時間以上勉強する子どもの割合は小6で37.1%、中3で58.9%。一方で、平日に2時間以上テレビゲームをする子は小6で37.1%、中3で41.5%。さらに、中3の53.3%が平日2時間以上スマートフォンや携帯を使用しているとの結果も出ています。
選択肢が増えた今、なぜ学力が下がるのか
私自身、20年以上教育現場に立ち続けてきました。その実感として、現在は「学力を伸ばすための選択肢」が圧倒的に増えています。対面指導、オンライン授業、コーチング型サポート―時代に合わせた多様な手段が整っています。
にもかかわらず、なぜ学力は下がるのでしょうか。
大きな要因の一つに「コミュニケーション能力の欠如」があると考えています。
「仲良しグループ」からの脱却
仲の良い友人同士だけでやり取りしていると、言葉が省略されても「空気」で通じてしまいます。主語や目的語を曖昧にしたまま意思疎通が成り立つ環境に慣れてしまうのです。
一方で、学力の高い生徒はこのコンフォートゾーンを抜け出し、第三者との会話を成立させます。さらに、良い意味で「厚かましさ」を持ち合わせており、講師に対しても臆することなく質問したり、教室の環境(エアコンの温度など)を率直に伝えたりします。
こうした積極的なコミュニケーションの積み重ねが、学びを深める大きな力になるのです。
会話ができる力が「学力」に直結する
コミュニケーション能力があれば、会話は成立します。そして、心の機微が分かるようになり、感情に流されずに「問題作成者の意図」を読み取ることができます。ただ知識を暗記するのではなく「どういう解答を作成すれば良いか」という本質的な理解に結びつきます。
▲AIによるコミュ力促進ツール
AIと人間の役割分担
もちろん、これからの学びにAIは欠かせません。効率化や情報整理には大きな力を発揮します。しかし、AIでは補えない部分―人と人との会話や、心の機微を理解する力―は、人間がしっかり支えていく必要があります。
学力低下のデータが出てしまった今だからこそ、私たち教育者と保護者が子どもたちに「学びの選び方」と「人との関わり方」を伝えていくことが大切だと感じています。