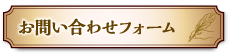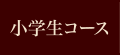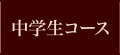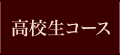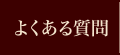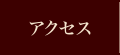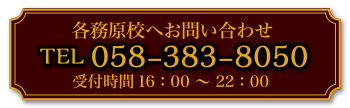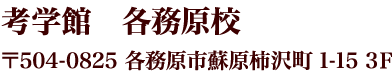当塾の全てのSNS(大学合格実績も2025版に更新済)
→https://lit.link/takashimizunogtmsteam
▲隅々までご覧下さい。
SNSの時代が、静かに変わり始めている
今、インターネットの歴史が始まって以来、初めてのことが起きています。
2022年をピークに、SNSの利用時間が減少に転じたのです。
世界的な消費者調査会社GWI(Global Web Index)のデータによると、これまで右肩上がりだったSNS利用時間が、2022年を境に下降し始めました。しかも、この傾向はすべての年齢層で見られます。特に注目すべきは、最もSNSを使っていた若い世代(16~24歳)が、最も早くSNSから離れているという事実です。
なぜ、このようなことが起きているのでしょうか?
AIが溢れるSNS、そして「本物」を求める人々
この変化の背景には、いくつかの大きな要因があります。
- AI生成コンテンツの氾濫
最近のSNSを見ていて、「これ、本物の写真?それともAI?」と疑問に思うことがあります。AIの進化により、SNSのフィード(タイムライン)には、人工的に作られたコンテンツが溢れるようになりました。美しすぎる風景写真、完璧すぎる文章、リアルに見える偽の画像…。「本物」と「偽物」の境界が曖昧になる中で、多くの人がSNSに疲れを感じ始めています。
- 「時間の奪い合い」への気づき
もう一つの大きな理由は、私たちが「時間」というものの価値に気づき始めたことです。SNSは、私たちの注意を引きつけ、できるだけ長く滞在させるように設計されています。無限スクロール、おすすめアルゴリズム、通知機能…すべてが「時間を奪う」ために最適化されているのです。特に若い世代は、この仕組みに早く気づき、「この時間、本当に自分にとって価値があるのか?」と自問し始めています。
- リアルな体験とつながりへの渇望
オンラインでの表面的なつながりではなく、実際に会って話す、一緒に何かを体験する―そうした「リアル」な人間関係を求める動きが強まっています。画面越しの「いいね!」よりも、目の前の人との深い対話。100人のフォロワーよりも、3人の親友。そんな価値観の変化が、データにも表れているのです。
次に来るのは「Slow Media(スローメディア)」の時代
では、SNSから離れた人々は、どこへ向かっているのでしょうか?
キーワードは「Slow Media(スローメディア)」です。
Slow Mediaとは、情報やメディアとの付き合い方を根本から見直す考え方です。具体的には、次のような特徴があります。
質を重視する
大量の情報を高速で消費するのではなく、少数の質の高い情報をじっくり読み、深く考える。一つの記事を何度も読み返し、自分の頭で咀嚼する時間を大切にする。
深いつながりを築く
浅く広い関係ではなく、少人数との深い信頼関係を重視する。顔も知らない数百人のフォロワーより、本音で語り合える数人の友人を大切にする。
体験の価値を再発見する
画面越しの疑似体験ではなく、実際に見て、触れて、感じる体験を求める。バーチャルな世界よりも、五感で感じられるリアルな体験に価値を見出す。
時間を「価値化」する
無限にスクロールして時間を「消費」するのではなく、自分にとって本当に意味のある活動に時間を「投資」する。
この「時間の奪い合い」から「時間の価値化」への転換こそ、私たちが今、直面している大きな社会変化なのです。
学びの本質も、「Slow」の中にある
ここで、私たちが大切にしている考え方とつながります。
本当の学びとは、Slow Mediaの考え方そのものです。
大量の問題を機械的に解くのではなく、一つの問題を深く理解すること。
多くの知識を浅く詰め込むのではなく、本質的な理解を時間をかけて築くこと。
オンライン動画を流し見するのではなく、先生や仲間と対話しながら、自分の頭で考え抜くこと。
SNS利用時間の減少というデータが示しているのは、単なるトレンドの変化ではありません。それは、「速さ」や「効率」だけを追い求めてきた時代から、「深さ」や「本質」を大切にする時代への、大きな転換点なのです。
時間を何に使うか
SNSを完全に否定する必要はありません。それは便利なツールであり、適切に使えば価値ある情報源にもなります。大切なのは、自分の時間を、自分でコントロールするということ。
流されるままに時間を消費するのではなく、自分にとって本当に価値のある活動―学び、成長、深いつながり、リアルな体験―に、意識的に時間を使う。
当塾では、そうした「時間の価値化」を実践しています。
じっくり考える時間、わかるまで対話する時間、自分の理解を深める時間。
それは一見、非効率に見えるかもしれません。でも、その「Slowな時間」こそが、本当の学力を育てるのです。
※本ブログのデータは、世界的な消費者調査会社GWI(Global Web Index)による、48カ国以上、27億人以上を対象とした調査に基づいています。